マッチングアプリはなぜ「もっといい人が現れる」と思ってしまうのか。
マッチングアプリを使っていると、マッチした相手がいても「もう少し探せば、もっと自分に合う人がいるのではないか」という気持ちになることがある。これは単なる気まぐれではなく、人間の心理とアプリの設計に深く関係している。私自身の経験や、同僚の事例を交えて、この現象の正体と抜け出す方法を探っていく。
レッツゴー!
「もっと合う人がいるはず」病
あるとき、マッチングアプリで条件も話も合う相手と出会い、順調にやり取りが進んでいた。それでも私は、ついアプリを開き、新着のプロフィールを眺めてしまった。理由ははっきりしている。「もっと自分とぴったりの人が、この中にいるのではないか」という淡い期待だ。
気づけば、相手とのやり取りよりもスワイプする時間のほうが長くなっていた。返信よりもプロフィール写真、会話よりも「次のマッチ」を探すことに意識が向かっていたのである。
週末ローテーション生活
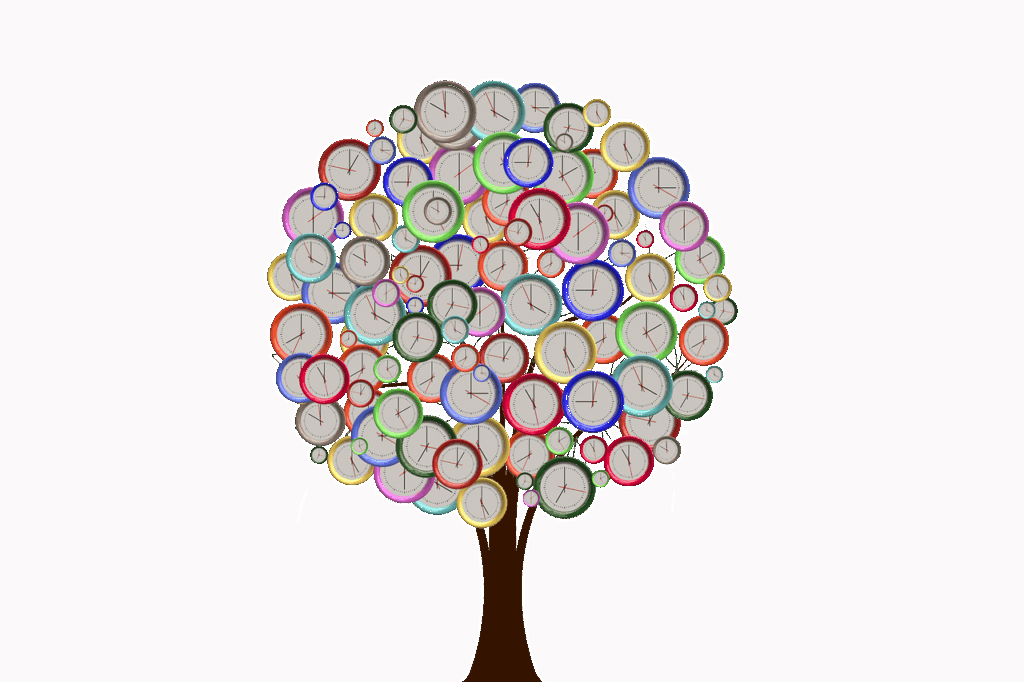
私の職場に38歳の女性がいる。彼女は35歳から複数のマッチングアプリを併用し、毎週末に必ず新しい相手と会っている。金曜日に予定が会えば1人、土日に1~多い時には4人。つまり、週によっては6人前後の初対面と会っている計算になる。
彼女は「依存とまではいかない」と言うが、その生活は3年続いている。会えばそれなりに話は盛り上がるが、次の週末にはまた別の相手と会う。どの人も悪くはないのに、決定打が見えないまま、延々と探索モードが続くのだ。
もちろんその中で、お付き合いした人はいた。しかし、結婚には至っていない。
彼女は自嘲気味にこう言った。
「パチンコや競馬と同じかもしれない。次は当たるかもしれないって、思っちゃうんです。」
なぜ終わらないのか――3つの心理メカニズム
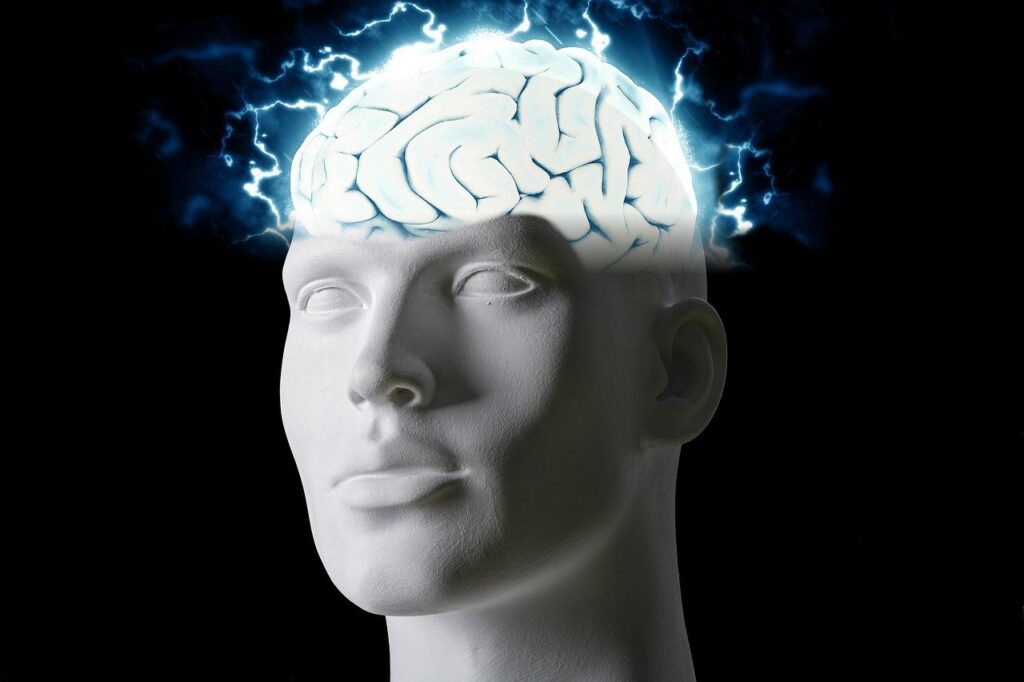
選択肢過多(パラドックス・オブ・チョイス)
心理学の研究によれば、選択肢が増えると人は決断を先延ばしにし、決めた後も後悔しやすくなる。アプリは無数の候補を提示し続けるため、「もっと良い人がいるはず」という気持ちが常に頭をよぎる。
変動比率強化(いつ来るかわからない当たり)
スワイプを何度しても、マッチという「当たり」は不規則にしか来ない。この不確実な報酬スケジュールは、スロットマシンや宝くじと同じで、最も中毒性が高いとされる。次のマッチを期待して、つい指が動いてしまうのだ。
FOMO(取り逃しへの恐れ)
アプリは常に「他の候補」を提示するため、今の相手に時間をかけるほど「他の良い人を逃しているのでは」という感覚が膨らむ。これが集中を妨げ、関係の深化より探索を優先させる。
あなたは探索モード依存か?
セルフチェック
- マッチの通知が来ないと落ち着かない
- 常に複数人と会話を並行している
- 2回目デート前に別の新規予定を入れる
- 「決めた後悔」を恐れてキープを作る
3つ以上当てはまるなら、探索が目的化している可能性が高い。
現場で見た「週末ローテーション」の落とし穴
同僚女性のように毎週新しい人に会う生活は、出会いの数は増えるが比較軸も増える。結果、どの人にも欠点が目につきやすくなり、誰にも決められなくなる。さらに、日程調整や初対面の会話など、精神的・時間的なコストが積み重なり、疲労だけが残る。
探索から「選抜・検証」へ切り替える方法

終わらないスワイプから抜け出すには、行動をルール化し、探索の上限を決める必要がある。
- 同時進行の会話は最大5人まで
- 週の新規面会は2人以内
- アプリ数は1〜2本に絞る
- 週1日はアプリ断ちをする
- 3回会ったら意思決定する
また、初回面会前に短時間の通話を挟み、相性を事前に確認すると効率が上がる。
まとめ
マッチングアプリの構造は、人間の意思決定の弱点を突いてくる。「次はもっといい人がいるかもしれない」という感覚は、心理バイアスとアプリ設計の組み合わせによって強化される。
だからこそ、自分なりのルールを持ち、探索に終わりを与えることが必要だ。出会いは手段であり、スワイプすること自体が目的になってはならない。決める勇気を持つことが、長期的な幸せへの近道である。
決して、マッチングアプリ自体が悪いわけではない。自身の思考と行動が大事である。

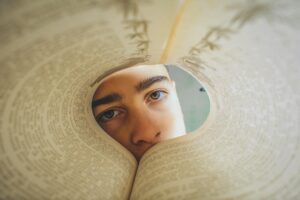
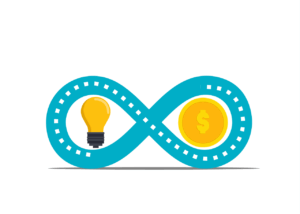
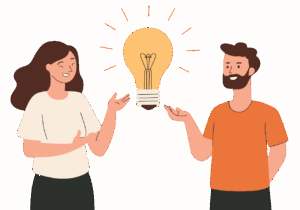





コメント